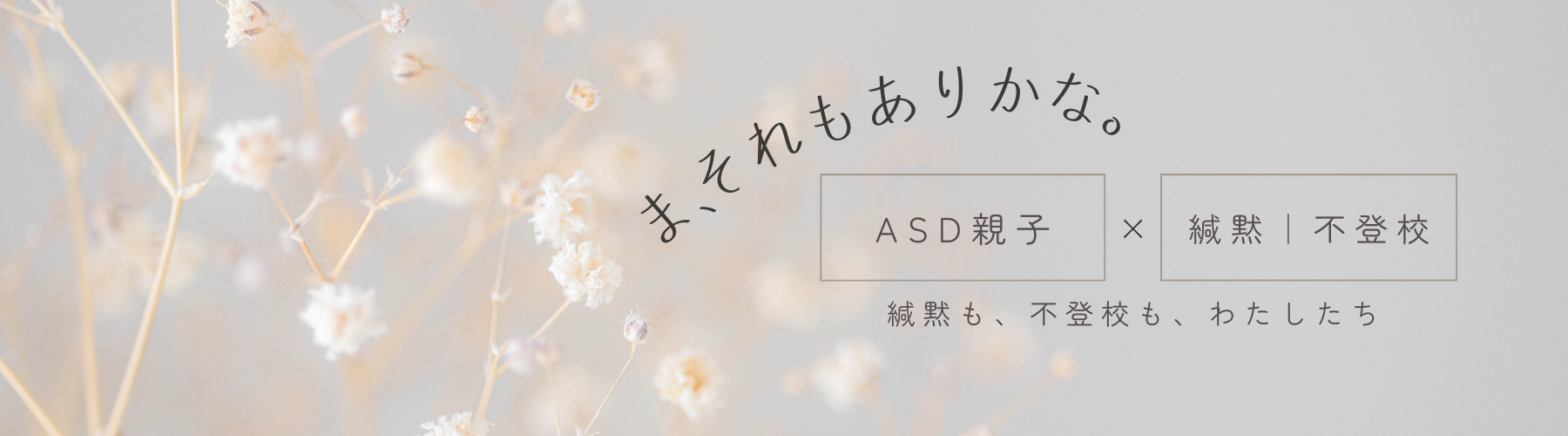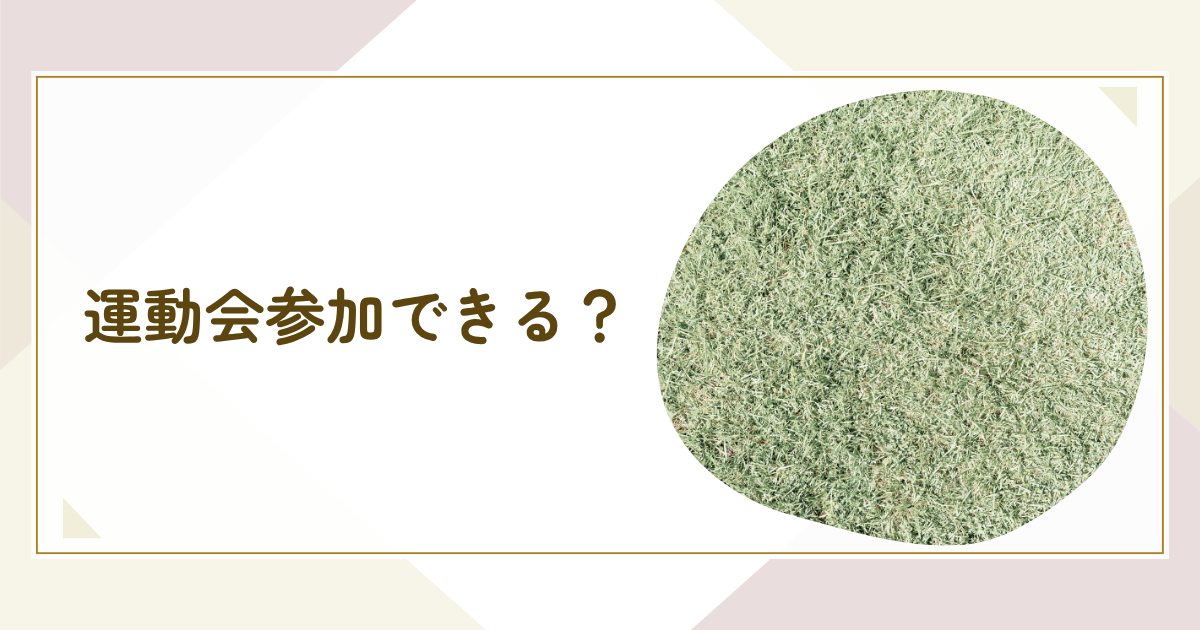かけっこだけの運動会――去年の涙と、今年への一歩
去年の運動会のこと
新学期が始まり、少しずつ学校生活のリズムが整ってくるこの時期。
ふと思い出すのが、長女が1年生だった頃の運動会です。
演目は「ダンシング玉入れ」と「かけっこ」。
でも実際には、練習にすらなかなか参加できず、
当日の体調や気分次第では「見学」や「欠席」という選択肢も視野に入れていました。
体操服には着替えられず、
イヤーマフと私服のまま校庭の隅に座っている姿を見たとき、
少しだけ胸が締めつけられたのを覚えています。
「かけっこだけ出てみる」決断
運動会の前日、長女に聞いてみました。
「どうする? 無理ならお休みでもいいよ」
すると、少しだけ迷ったあとに、
「かけっこだけは、出てみる」と。
その理由は、「じいじが応援してくれるって言ったから」。
ごほうびがあるという言葉も、背中を押してくれたのかもしれません。
ただ、前日から「1番になれなかったらどうしよう」と、
ずっと不安を抱えていました。
勝ち負けに強くこだわってしまう長女。
じゃんけんすら最近ようやくできるようになったくらい、
“負けること”に対する苦手意識が強い子です。
だから、「出てみる」と自分で決めたその一歩が、
どれほど大きなことだったか、今でも忘れられません。
私なりの付き添いと心の葛藤
当日は、開会式も準備体操もダンシング玉入れもパス。
出番の直前まで、私のそばで静かに待機して、
タイミングを見てひょこっと合流するスタイルでした。
他の子と違う参加の仕方かもしれません。
でも、それが娘にとっての「精一杯の参加」でした。
そして私はというと、
かけっこが終わった直後に娘をスムーズに迎えに行けるよう、
保護者が本来入れない教職員専用エリアに特別に入らせてもらっていました。
もちろん、事前に先生方と綿密に打ち合わせをして、
声をかけてもらえるタイミングなども確認済み。
それでも、周囲の保護者の視線は気になってしまって…。
「なぜあの人だけ中に?」「どんな事情があるの?」「見やすい場所でずるい」」
そんなふうに思われているかもと、勝手に想像しては胸が痛くなっていました。
でも、先生が「もうすぐですね」と声をかけてくれたあの瞬間。
その一言に少しホッとしました。
私も、私なりに「やりきった運動会」だったと思います。
とにかく娘のために——
人目は気になるけど、「がんばれ私!」って心の中で何度も言い聞かせながら、
どうにか踏ん張って、乗り越えました。
今年の運動会への準備
そして今年。
去年は2学期に入ってから練習が始まっていましたが、
今年は早めに子どもたちに運動会のことを知らせて、
徐々に準備していく方針になったそうです。
私は、先生にお願いしました。
- 動きの流れを、図などで視覚的に伝えてほしいこと
- スタートの合図の「音」が苦手なので、旗などに変更してほしいこと
どちらも、娘にとっては大切なサポートです。
先生方が快く対応してくださって、
本当にありがたい気持ちでいっぱいです。
少しだけ“わかっている安心感”
去年、本人なりに「運動会ってこういうものなんだ」と
体感できたことは、今年への安心感につながっている気がします。
もちろん、また不安になったり、
急に参加できなくなったりすることもあるかもしれません。
でも、親子で去年を一度経験できたからこそ、
今年は少しだけ、心の準備がしやすくなっている。
無理をせず、でも確実に。
今年の運動会も、「この子なりの参加のかたち」で
安心して迎えられるよう、準備を整えていけたらと思っています。